こんにちは。助産師かこです。
看護師にとってとても重要だと思うのが「コミュニケーションスキル」。
日々の業務で、
「患者様に寄り添いたいけど、本当の思いをなかなか引き出せない」「会話が続かなくて、沈黙が怖い…」と思ったことはありませんか?
そのお気持ち、深くうなずいてしまいます。
何を隠そう実は私、人と話すのがとっても苦手なんです…。

今でこそ利用者様には「嘘だー!」なんていわれることも増えてきましたが…。今日も日々お喋りに緊張して、沈黙を恐れ、失敗して、また勇気をだしてお喋りをしています。
そんな私も、コミュニケーションスキルを学びながら実践していくうちに、利用者様との時間が居心地のいいものになっていたり、ぽろっと本音を話してくれたりする機会が少しずつですが増えてきました。
ぜひ同じ悩みを持つ方と一緒に、少しずつ前に進められたらと思い、私が経験したことやうまくいったよ!なんてことを共有させていただけたらと思います。
今回の記事で分かること
・「傾聴」のメリット
・「傾聴」の方法
・「傾聴」を実践してみて経験したこと
「傾聴」のメリット
今まで私は「傾聴」なんて、話を聞くってことでしょ?と単純に思っていたのですが…。看護の中でコミュニケーションスキルとして意識して使ってみると、利用者様はもちろん、私自身にもメリットがありました。
利用者様のメリット
まず、改めて傾聴について。利用者様のメリットは
・利用者様自身に「自分の気持ちを受け止めてもらえた」という安心感
・「支えてくれる人がいる」孤独感の軽減
・不安やつらさ、または楽しいこと嬉しいことを共有して気持ちの整理ができる
・「あ、私こう思っていたんだ」と自分の考えに気づける
・「ちゃんと私の話を聞いてくれる」と信頼関係が深まる 等
利用者様にとってじっくり傾聴をしてもらう時間は「ただ話を聞く」だけではなく、大きな支えになるケアになってきます。
看護者自身のメリット
では、看護者自身はというと、「自分を知ることができる」これが大きなメリットになると思います。利用者様を知りたい!と思っての傾聴が、自分自身の気持ちを振り返るきっかけに。
例えば、
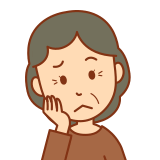
私、料理するの苦手なんだよね。
と、言われたとき私の中では
・苦手なことを教えてくれた!
・困ったことがあったのかな?
・何か話そうときっかけを作ろうとしてくれたのかも
・私も料理苦手だな…
・なんて答えるのがいいんだろう 等々、頭の中では色んなことを思います。
嬉しさだったり、疑問だったり、共感や戸惑いなど様々。心の中では自分の気持ちを認識しつつ、思うがまま喋るのではなく、利用者様がなぜこの話題を出したのかな、どんな思いから出てきたのかなと利用者様を知ることができるような言葉や質問を選んでいくようにします。
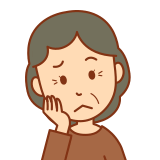
この間、味付けが上手くいかなくて。こんなことがあったんだよねー。
なんて利用者様の話があると、私自身「あ、自分語りを始めてくれた」と思います。看護者の自己肯定感にもつながっていくのかなと思います。
私は、お仕事の中で意識して続けていくうちに、普段の生活でも自分の感情の変化に気づくことが増えたように思います。
「傾聴」の方法
メリットがわかった次は、やっぱり実際の看護の中で、スキルとして「傾聴」はどうやって使ったらいいの?というお話になります。
看護者の語りは多くて3割
・看護者と利用者の語りの割合はずばり、1~3割(看護者)対7~9割(利用者)と言われています。

喋り下手な私はこれを知って、あ、1割でいいんだとほっとしました。
看護者が話しすぎてしまうと、利用者様のペースや考えを押し流してしまいます。看護者の話す割合はグッと減らし「この人なら聞いてもらえる」という安心感を作ります。
3種類の傾聴
傾聴は3種類もあるのをご存じでしたか?
もしかしたら看護学校時代に習ったのかもしれませんが…、私は頭に入っていませんでした。
受動的傾聴
非言語的なコミュニケーションをメインとして、安心して話せる空間を作る方法です。
- 利用者様が安心して話ができるような環境設定をさりげなくします
(部屋選び、室内様子、看護者の服装等) - 評価や判断をせずに受け止める姿勢を大切に
- 相づちや頷き、アイコンタクトで「聴いている」ことを表現する
(時には目線を外すのも必要。) - 沈黙も非言語的コミュニケーションの一つとして大切にして、あえて作ってみる
(利用者様の考える時間だったり、ペースを合わせたり、その間は看護者もアセスメントができたり。)
反射的傾聴
ただ聞く、から一歩進んで「聴いてますよ」というメッセージを返す方法です。
- オウム返し(言葉を返す)
- ミラーリング(表情、姿勢やジェスチャーを返す)

普段の生活でもオウム返しは、意識せずにやってたりしますよね。
普段何気なくやっていた傾聴も頭で意識して、意図的に技法として使うようにしています。
そして、利用者様がいつの間にか自身に向き合って、自身について考えられるように、促していきます。
積極的傾聴
最後に、相手の気持ちに寄り添って、関心をもって聞いていく方法です。
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを使い分けながら、利用者様の語りに合わせて質問を選んでいきます。
例えば、まだまだ関係性ができてないうちにオープンクエスチョンばかりだと答えづらかったり、クローズドクエスチョンだけだと話が深まりません。その時の話の流れに合わせながら選ぶように気を付けています。
「傾聴」を実践してみて経験したこと
では、実際に訪問の現場で私が「傾聴」スキルを使ってみてどうだったの?というところ、経験したことをご紹介します。
なかなか話をしてくれなかった利用者様
赤ちゃんを育てながら療養生活を送っている利用者様。初回の訪問では、視線はほとんど合わず、クローズドクエスチョンに答えてもらうのがやっと。「私が来ること自体が負担になっているのかな…?」と感じるほど緊張感がありました。
傾聴スキルを使いながら訪問を重ねて…
受動的傾聴として
訪問回数を重ねていくうちに、座る場所の距離を近づけていきました。位置もできるだけ対面ではなく、90度に、そして笑顔が見られるようになってきたころには横並びへ。
視線はずっと合わせるのではなく、わざと外したり、赤ちゃんを一緒に見たり。
姿勢も本人が崩していれば一緒に崩しめにするよう(くだけすぎないように)配慮して、緊張感も取れるように意識してみました。
積極的傾聴として
1回の訪問の中で、会話の最初はクローズドクエスチョンを使って、答えやすい話をしていきます。徐々に会話の流れや、クローズドクエスチョンをしていく中で、今日の調子や気分を感じ取りながら、オープンクエスチョンに変えていきました。オウム返しやミラーリングも混ぜ込みながら。
例えば、予防接種の話題があったときは
私「この間、予防接種でしたよね、行けました?」
利用者様「はい、行けました。(何か思い出してそうな様子あり)」
私「行けたんですね。〇〇ちゃん頑張りましたね。どんな様子でした?」(オープンクエスチョン)
利用者様「打った時はほとんど泣かずに打てたんですよ。強かったです。でも帰ってから夜熱が出ちゃって大変でした。」
私「そうだったんですね、熱出ちゃったんですね、大変でしたね。」(反射的傾聴で受け止め、リアクションも大きめに)
利用者「はい、初めての熱で。眠れない様子で辛そうで。ずっと抱っこしてないと泣いちゃっていられない感じでしたね。…」
と、何か思う部分がありそうだなということが感じられれば、オープンクエスチョンを取り入れたり気持ちが出せるように質問を選んでいきました。
少しずつ心を開いてくれた瞬間
何度も訪問を重ねるうちに、「人付き合いするのは難しい、辛い。」と打ち明けてくれました。その後は少しずつ笑顔が増え、子育ての楽しいことや日常生活の困っている出来事を「実は…」と話してくださるようになりました。
私も、日によって「あ、今日はなんだか調子が悪そうだ」「いつもより表情が暗いな」「今日は目線がよく合う」と違和感に気づけるようになってきたと感じています。
まとめ
今回の記事の中ではうまくいった時の経験談も載せましたが、もちろんうまくいかないことも多く、「私が訪問する意味はあるのだろうか…」「他のスタッフの方が話しやすいのではないだろうか…」と悩むことも少なくありません。
そんな時は、他のスタッフさんと相談して、私も傾聴をしてもらったり、自己対話をして客観的になれるように心がけています。
記事をここまで読んでくださったあなたはきっと、多少何か気になっていることがあるのかなと思います。少しずつできることから、一歩を踏み出すきっかけになれたら嬉しいなと思います。
私も一緒に頑張ります。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
また次回!



コメント