娘ちゃんは、小学2年生なります。現在、彼女の心を一番に占めているもの―
それは「ゲーム」。
中でもニンテンドースイッチの「スプラトゥーン」です。
ゲームに夢中な娘をみて、ちょっと複雑な気持ち
思えば、これが初めて自分で遊んだゲーム。
約1年前、我が家にニンテンドースイッチがやってきてから、娘ちゃんの世界が大きく変わり始めました。
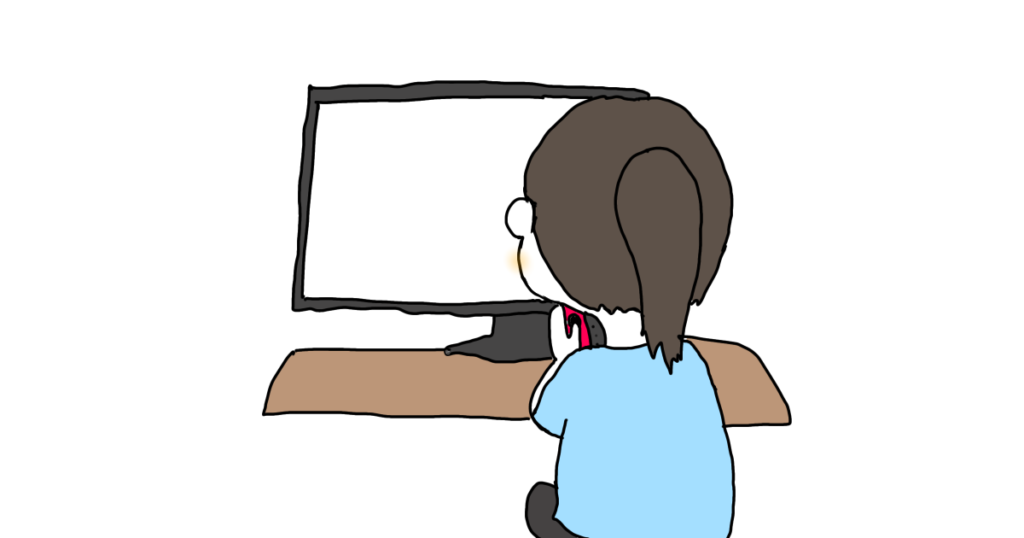
それまでは、シルバニア、プリンセス、プリキュア、すみっコぐらし…と興味の移り替わりが早く、何か一つのことに長く夢中になることが少なかった娘ちゃん。
「いつか何か夢中になれるものと出会えたらいいな」と親として思っていました。
「ハマる」って悪いこと?母の中の葛藤
もともと両親ともにがゲームやアニメ好きなので、「きっといつか通る道だろう」と思いながらお迎えしたゲーム。
そして案の定、娘ちゃんは一瞬でその世界に夢中になりました。
正直、母としては悩ましいこともあります。
「ゲームばかりしていて大丈夫かな?」「視力や姿勢への影響も心配・・・」
そんな想いが頭をよぎる日もあります。
でも同時に「ここまで夢中になれるものに出会えたこと」は、彼女にとってとても貴重な経験なのかもしれないなとも思いました。
助産師ママが感じた“夢中になる力”の意味
助産師としては、これまで多くの親子の関わりを見てきて感じるのは、子どもが何かに熱中することは「自分の世界を築く力」につながるということ。
夢中になる時間の中で、子どもは“自分で工夫する力”や“失敗しても挑戦する心”を育てているように思います。
スプラトゥーンは、チームバトル戦の中で他者との協力を学んだり、自分の戦い方や立ち位置を考えたりと、実は思考力や社会性の種が沢山隠れているなと感じることもあります。
ゲームを頭から悪のように線を引かずに、子どもが夢中になっているものに、一緒に同じ目線に立って、先を見てみる。
そうすると、ちょっと面白い世界がみえてきたんですよね。

ただ、日常生活はバランスも大切かなと思い、一緒に時間など約束を決めて、タイマーを持たせて自分で管理してもらうようにしています。
共感し、見守ることで育つ「自分の世界」
私も余裕があれば、ゲームをやっている娘ちゃんの隣に座って、ゲーム観戦をさせてもらうことも少なくありません。
「どんな作戦でいくの?」「この武器はどんな攻撃が得意なの?」「このお洋服すごいかっこいいね!」と話をしてみるようにしています。
すると、娘ちゃんは目を輝かせて私の理解を超えて、「え?そんなことまで知ってたの?」「こんなこだわりが詰まってたの!?」なんて、話をちょっと止まることなくしてくれます。
“あぁ、今、この子は自分の世界を一生懸命深く、広く、濃く、鮮明に作っているんだな”と感じます。
ちなみに、昨年のクリスマスには、サンタさんから『スプラトゥーンのイラスト集』をプレゼント。
すると、夢中でキャラクターの絵を書くようになりました。
“ゲーム”がきっかけで“創造の世界”にも広がっていった瞬間です。

実はそこにさらに母お手製のハロウィーン衣装も加わりますが、それはまた別のお話で。
次なる悩みは「スイッチ2」問題?!
そして今、話題の「スイッチ2」。
新しいスプラトゥーンが出るとか出ないとか・・・。
母の頭を悩ませる日々は続きそうですが(笑)、こうして何かに夢中になっている姿を見られるのは、やっぱり幸せなことなのかもしれません。
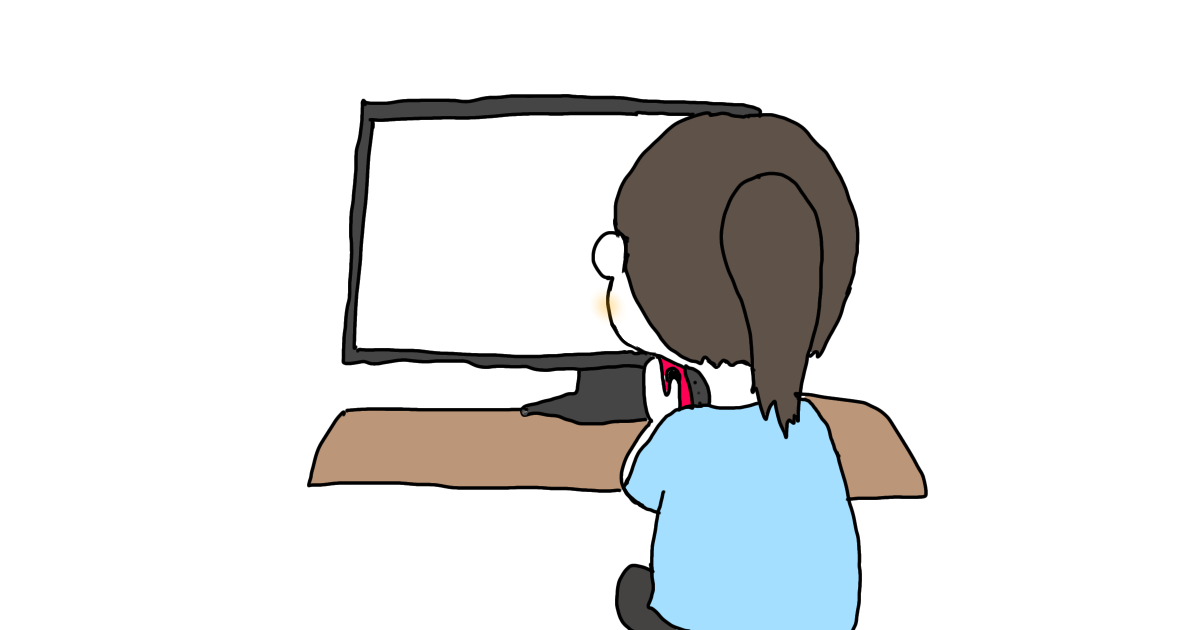


コメント