前編では、私がどのように育児ノイローゼに陥ったのか、その当時の気持ちを書きました。
今回はその続きとして、そこから気づいたことや学んだこと、また、同じように悩んでいる方に向けて、記事を書かせていただきます。
助産師でも育児は初めて
一番最初に伝えたいことは、「助産師でも我が子の育児は初めて」ということです。
知識はあっても、自分の子どもを育てるのは別の話。
私は助産師として、1日の勤務が長くて夜勤約17時間でした。
ただ、17時間の勤務の中で一人の赤ちゃんにずっとつきっきりで過ごすわけではなく、途中でお産があったり、出産後のケアがあったり、何人もの赤ちゃんの授乳をしたり、お母様のおっぱいのケアをしたり…。
そうなんです。
我が子を産み、育てるまで、一人の赤ちゃんと24時間ずっと一緒に過ごす経験はなかったんです。

産まないと助産師になれないとは、まったく思いません。
ただ、私にとって我が子の育児は、助産師観が大きく変わる出来事になりました。
授乳や抱っこは手技として知っているけれど、授乳や抱っこをしても泣いている、何時間抱っこしたらいいのだろう、私もいつ寝たらいいんだろう、このミルク・おっぱいでちゃんと体重は増えてるの?、具合が悪いのではないよね?この発疹は?と、一緒にいて見れば見るほど気になって不安の嵐…。
そして当時の私は「助産師なのに」と自分を追い詰めていました。
でも今思えば、それは当たり前のこと。
知識があっても、母としての経験はゼロから始まったばかりだったんです。
頼ることは甘えじゃない
私は「育児は頼らない」と決め込んでいたのかもしれません。
時代が少し前の親のアドバイスが苦しかったこともありましたが。「自分でやらなきゃ」という思い込みが強すぎたのだと思います。
誰かに頼ること、助けてもらうことは、自分や我が子を守るために必要なこと。
育児は一人ではできない。
頼れる相手が家族でなくても、友人でも、支援センターでも、地域の保健師さん助産師さんでもいい。
少しでも気持ちを吐き出す場所があれば、あの孤独は違ったのかもしれません。
親世代のギャップから学んだこと
親世代の「母乳神話」や「泣かせておけばいい」という考え方は、当時の私には辛いものでした。
でも今思うと、それは「その時代やその人にとってのベスト」だったのだと思います。
時代によっても、医療は進んで新しいエビデンスも出て、育児の常識は変わっていく。
今の私が正しいと思うことも、将来は変わっているかもしれません。
だからこそ、「色んな価値観があっていい。」という学びをもらった気がします。
自分が子どもに接するときも「こうすべき」で縛るのではなく、「それもいいね」と思えるようになりました。
あの頃の私に伝えたいこと
あの頃の私に会えるなら…
「辛くない?大丈夫だよ。とても頑張っているよ。」
「助産師だからなんて思わなくていい。初めてお母さんになるんだから。」
「少し、一緒に話そう。」
と、まずは話を聞きたい。
当時は、自分を責めることばかりでした。
でも、泣きながらでも、必死に抱っこして、授乳して、おむつを替えていた。それだけで十分頑張っていたんです。
戻れるなら、もっと肩の力を抜いて、一人目の育児のスタートを楽しみたかったです。

今の私は、育児は手を抜き、力を抜き、楽しみ足して、ついでに昼寝。
そんなモットーで過ごしています。
今、同じように悩んでいるあなたへ
もし今、真っ暗な部屋で赤ちゃんを抱っこしながら涙を流している人がいたら。
どうか知ってほしいです。
助産師の私でさえ、あんなに泣いて。あんなに迷ってあんなに苦しんでいたことを。
あなたが泣いてしまうのは、弱いからじゃありません。
それだけ赤ちゃんに真剣に向き合っているからです。
「私もそうだったよ」とお伝えすることが、少しでもあなたの心を軽くできますように。
おわりに
一人目の出産は、喜びと同時に沢山の孤独や不安を伴いました。
助産師でも、育児はゼロから。
出来なくても、泣いてしまっても、母としても価値は変わりません。
これからも私は助産師として、母として、誰かに寄り添える存在でありたいと思っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ではまた次回の記事で。
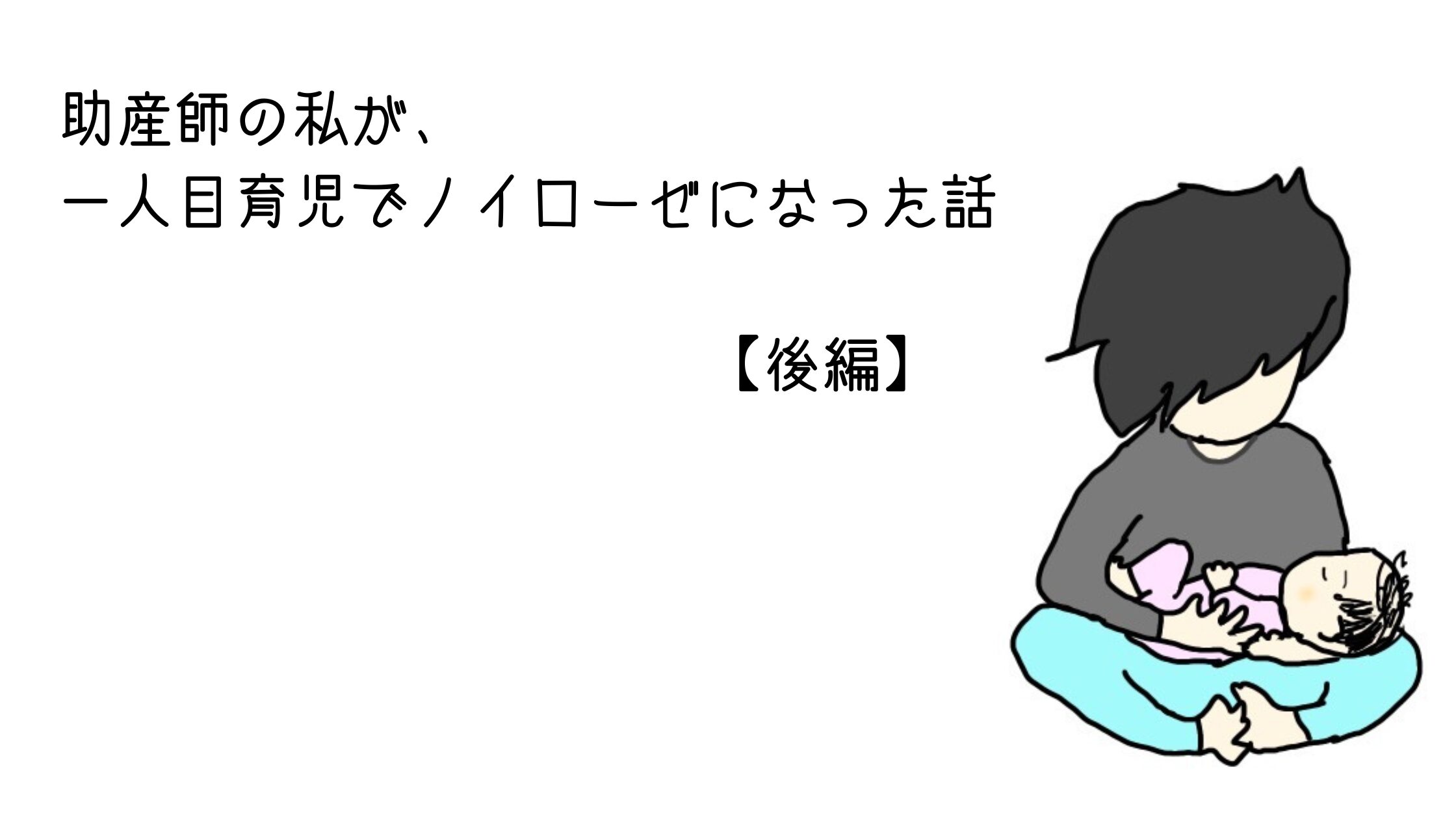



コメント